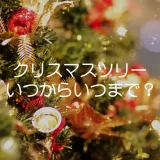毎年クリスマスシーズンになると、何気なく使っている「メリークリスマス!」というフレーズ。
クリスマスをお祝いするポジティブな言葉なのはなんとなくわかっていても「メリーってどういう意味だろう」と気になったことはありませんか?
今回は、案外知られていない「メリー(marry)」という言葉の意味や「メリークリスマス」以外に使える英語のクリスマスのあいさつをご紹介します。
そもそも「メリークリスマス」ってどういう意味?

「メリークリスマス(Merry Christmas)」を日本語にすると「素敵なクリスマスを」「クリスマスおめでとう」といった意味になります。
「メリー(marry)」には「陽気な」「楽しい」「お祭り気分の」といった意味があり、「メリークリスマス」は楽しいクリスマスをお祝いしようというポジティブなあいさつです。
ところで、この「メリー(marry)」という形容詞、クリスマス以外ではめったに見聞きすることがありませんよね。
日本語訳だけ見ると「メリー」以外の言葉でも良さそうな気がしますが、なぜ「メリークリスマス」というフレーズが一般的になったのでしょうか。
「メリー(merry)」がクリスマスとセットで使われる理由

現在「marry」は英語圏の日常会話でもほとんど使われておらず、やや古めかしい印象があります。
それでも「メリークリスマス」というフレーズが未だに残っているのは、現代にも歌い継がれているクリスマスソングの影響が大きいようです。
「We Wish a Merry Christmas」は日本人でもきっと一度は聞いたことがある有名なクリスマスキャロルですが、その起源は16世紀に遡るといわれています。
日本語でも「好きこそものの上手なれ(~こそ~なれ)」「百聞は一見に如かず(如かず:及ばない)」といったことわざがありますが、同じように「日常会話では使わないけれどフレーズとして定着している」という感覚なのかもしれません。
「メリー(merry)」と「ハッピー(happy)」の違い

メリーとハッピーはほとんど同じような意味に見えますが、メリーには「浮かれた」「ほろ酔い気分の」というニュアンスも含まれています。
現在ではこの単語は未成年などに使うのはふさわしくないとして、イギリスでは「ハッピークリスマス(Happy Christmas)」というフレーズがよく使われるようです。
また、最近では宗教的な理由でも「メリークリスマス」というフレーズは使われなくなってきています。
日本以外の国では「メリークリスマス」をあまり使わない

日本では「クリスマス=宗教行事」という感覚がなく、信仰している宗教にかかわらず年末のイベントとして楽しむ人がほとんどです。
しかし、さまざまなバックグラウンドを持つ人々がいる欧米諸国では、クリスマスをお祝いしない人も大勢います。
「クリスマスおめでとう!」というあいさつに不快感を示す人に配慮し、最近では「クリスマス」という単語が入っていないフレーズを使う人が増えてきているのです。
「メリークリスマス」以外の英語のあいさつ

宗教に関係なくクリスマスシーズンに使える英語のあいさつは次のようなものがあります。
相手の宗教がわからない場合や、英語圏の方へのクリスマスカードなどに使ってみてください。
「Happy holidays.(良い休日をお過ごしください)」
クリスマスではなく「休日」を楽しんでね、というニュアンスなので、欧米諸国では宗教色のない年末年始のあいさつとして広く浸透してきているフレーズです。
クリスマスや年末年始以外の休暇にも使えます。
「Season’s greetings.(時候のご挨拶を申し上げます)」
クリスマスカードやメールの件名などに使うことが多い文語的な表現です。
目上の方やビジネス相手への年末のあいさつにも使われます。
「Have a happy new year. / Wishing you a happy new year.(良いお年を)」
「ハッピーニューイヤー」は日本では年明けのあいさつとして定着していますが、英語圏では「良いお年を」というニュアンスで年末にも使われる言葉です。
「Happy holidays and wishing you a happy new year.」というように、クリスマスと新年のあいさつを一緒にすることもよくあります。
その他の英語のクリスマスメッセージはこちらも参考にしてください。
 【贈る相手別】クリスマスカードのメッセージ例文
【贈る相手別】クリスマスカードのメッセージ例文
今年も楽しくクリスマスを過ごそう!
毎年当たり前のように使われているけれど、繊細なニュアンスはあまり知られていない「メリー(merry)」の意味についてご紹介しました。
もし機会があれば「メリークリスマス」以外のあいさつも使ってみてくださいね。Happy holidays !